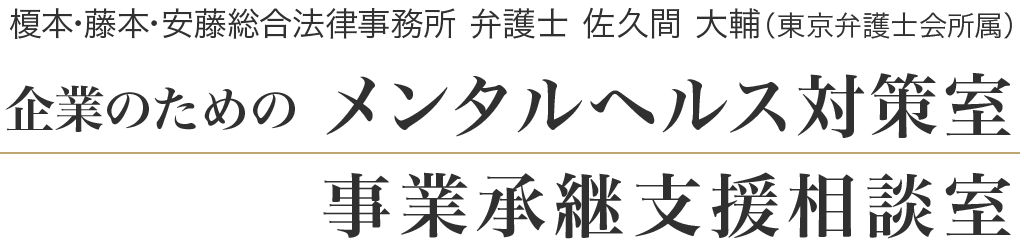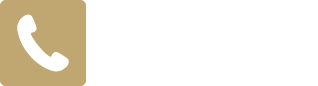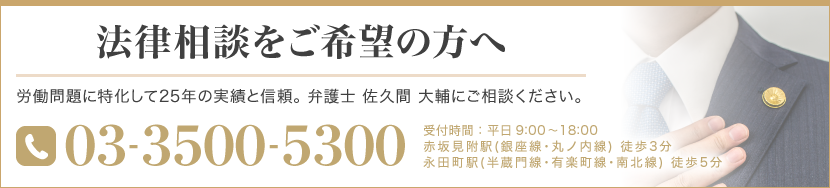カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは
過労死等防止対策大綱は、「サービス産業を中心に、一部の消費者及び生活者から不当な要求を受け、日常の仕事に支障が生じ、労働者に大きなストレスを与える事例も問題となりつつある」と指摘しており、カスタマー・ハラスメントが社会問題化しています。
パワハラ防止法に基づき告示されたパワハラ防止指針は、事業主に対し、取引先等の他の事業主が雇用する労働者等または他の事業主からのハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為により、その雇用する労働者が就業環境を害されることがないよう、雇用管理上の配慮を行うよう求めています。クレームが増加する状況を受け、企業の実情に応じて職場を支援する体制を整備することが必要となりました。
顧客からクレームを受けたとき、契約上の信頼関係を維持することを基本方針として、迅速かつ誠実に対応します。そのため、顧客を最初からクレーマー扱いするのではなく、その内容や態度が社会通念上相当であると認められる場合は、製品やサービスの改善につながる可能性があるので、前向きな姿勢を持って取り組むことが必要です。
これに対し、クレームの内容や態度のいずれか、またはその両方が不相当である場合は、クレーマーとして捉えて、親身な態度は維持しつつも、毅然とした態度を示さなければなりません。
この対応が適切に行えずにクレームが紛争に発展すると、顧客が損害賠償等の請求をしてくることがあります。その際に、提訴や判決の記者会見が行われてその内容が報道され、さらにインターネット上でも広まると、企業のイメージダウンとなり、消費者、取引先、金融機関等のステークホルダーの信用低下につながります。
顧客から請求がなされた段階でも、企業が顧客との信頼関係を基礎とした対応をすると、紛争の発生や長期化というリスクを減らすことができるので、企業の収益に結びついてきます。
そこで、本講座では、クレーム対応業務に従事する労働者のメンタルヘルス不調を予防する使用者の義務を学習するとともに、製品やサービス等に不満を持つ顧客が企業に接触する段階から、損害賠償等の請求をするに至る段階まで、各時点における企業の適切な対応方法を選択問題を交えつつ解説します。
◆クレームから企業を守る
◆クレームから従業員を守る
◆労働者側との初回面談までの対応
◆初回面談時における対応
◆顧客の要求への対応
◆証拠開示や社内調査への対応
◆損害賠償等の請求への対応
◆サービス・リカバリー・システム
研修以外のコンサルティング(法的助言・提案)に関しましては、次のページをご覧ください。
>>「パワーハラスメント防止対策リーガルサポートサービス」
【講演料】
弁護士佐久間大輔の構成した内容をベースにした講演料は、3時間165,000円(消費税含む)です。
講演だけでなく、これを踏まえて従業員参加型のワークショップを開催すると、メンタルヘルスケアや労災事故防止に有効であるといわれており、時間延長も承ります。
なお、交通費や出張日当が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。
【DVD】
株式会社ブレインコンサルティングオフィスより、上記と同名のDVDが発売されています。
カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!(同社のサイトにリンクします)
【関連コラム】
ProFuture株式会社が運営する日本最大級の人事ポータルサイト「HRpro」に、「顧客からハラスメントやクレームを受けた従業員を守るためのマネジメント」と題するコラムを寄稿しました。
顧客や取引先からの悪質クレームなどのハラスメントという外部環境からの脅威より従業員を保護するために管理監督者や人事労務担当者の取るべき対応について解説しています。
顧客からハラスメントやクレームを受けた従業員を守るためのマネジメント
(HRproのサイトにリンクします)
- 労働安全衛生マネジメントの企業研修
- 若手SEのうつ病・自殺予防-メンタルヘルスケアは未然防止が重要!管理職が果たすべき義務と対応の手引き
- 職場で高ストレス者が出たらどう対処する?-ストレスチェック実施後の疾患予防策
- 休職・復職トラブル回避の手引き-企業が果たすべきメンタル不調の病休対応
- 就業上の措置をめぐる労働契約の変更に対応するには-労使双方の情報共有による合意形成の実務
- 労基署が臨検に入ったらどう対処する?-是正勧告を受けないための残業リスクアセスメントのすすめ
- パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対処する?-パワーハラスメントにおけるリスクマネジメント
- パワハラ上司が訴えられる!使用者責任を問われないために-ラインケアでパワハラを予防する
- カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは
- メンタルヘルス不調による損害賠償請求をどう解決するか-労働者側から請求されたときの対応方法とは
- 企業がトラブルを発生させないための健康情報の取扱い-個人情報保護法に基づく実務上の対応とは